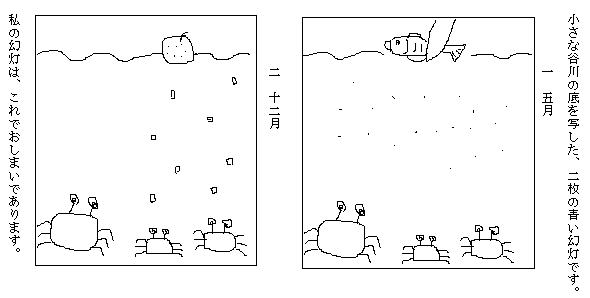
(C)Talk Line/小学校/国語/やまなし/6年/向山型国語/向山型分析批評
大阪法則化サークル「淀川部屋」/中原 勇治
「スクリーンの位置はどこですか。」は、『やまなし』「視点」の授業で向山先生がなさった有名な発問である。
しかし、いきなり「スクリーンの位置はどこですか。」と問うても子どもたちからなかなか意見が出ない。
そこで、幻灯の絵を描かせたうえで「スクリーンの位置」を問う授業を試みた。
第1時
指示 全員起立。「やまなし」を1回読んだら赤鉛筆で○を1つ塗って座りなさい。
座ったら「やめ」というまで読んでおきなさい。
指示 4ページ1行目「小さな谷川の底を写した、二枚の青い幻灯です。」を指差しなさい。
となりの人は押さえていますか。みんなで読みます。さんはい。
指示 それをそっくりそのまま、ノートの新しいページの1行目に写します。
指示 もう一度みんなで読みます。
発問 「幻灯」とは何ですか。
・写真のフィルムに光を当てて拡大し、スクリーンに映してみせるもの。スライド。
発問 「幻灯」がもう一ヶ所出てきます。どこですか。
・一番最後のところ。
指示 そう、一番最後のところ。指差しなさい。みんなで読みます。さんはい。
「私の幻灯は、これでおしまいであります。」
指示 それをそっくりそのまま、さっき写したページの一番最後の行に写しなさい。
発問 「幻灯」は何枚ありますか。
・二枚です。
発問 一枚目の幻灯はどこからどこまで書かれていますか。教科書に線を引きなさい。できたら前に持ってきます。
・P.4 L.2「一 五月」~P.11 L.4「すべりました。」まで。
発問 二枚目はどこからどこまで書かれていますか。
・P.11 L..5「二 十二月」~P.16 L.7「はいているようでした。」まで。
指示 では、ノートの最初と最後の文の間に「一 五月」「二 十二月」と書いて、二枚の幻灯の様子を絵に描いて表しなさい。
「五月」の絵が描けたら前に持ってきます。
・「よく描けてるね。」とほめながら○をつける。
・中には一枚で書ききれないので二枚に分けて描く子もいる。
・「五月」の絵が描けたら「十二月」の絵を描くように指示する。
・「十二月」の絵を書いて持ってきた子に、黒板で書かせる。
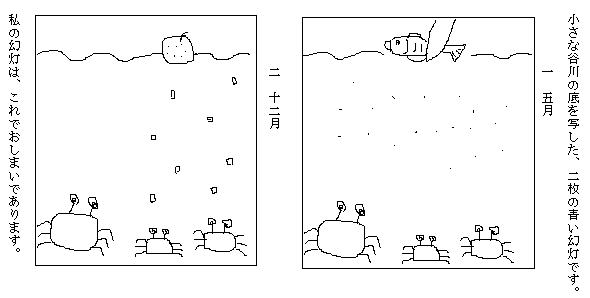
指示 前に描かれた絵について意見がある人はどうぞ。
指示 絵を描いていて「あれ、変だ。」「おかしい。」と思ったことをノートに書きなさい。
・教科書では魚が動いたり、カニの兄弟たちがしゃべっていて動いているので、一枚の絵に描きにくい。
・4ページ3行目に「青い幻灯です。」と書いているのに、「銀の色の腹」や「日光の黄金」「白い岩」などいろいろな色が出てくるからおかしい。
・スライドはしゃべったりしないのに、カニの兄弟がしゃべっているのがおかしい。
第2時
説明 「幻灯」を写すためにはスクリーンが必要です。この二枚の幻灯はどこかのスクリーンに写っているのです。
発問 では、二枚の幻灯が写っているスクリーンの位置はどこですか。絵に描いて表しなさい。
次のような絵がでた。
A.話者の頭の中・心の中
B.話者が持っている・写している
C.川の底
指示 では、その理由・根拠をノートに書きなさい。
指示 では、意見の発表をします。机をコの字型にしなさい。どなたからでもどうぞ。
<A.話者の頭の中・心の中>
・「やまなし」は物語なので空想。
・カニがしゃべっていることなどは写真にできない。話者が頭の中で想像している。
・カニは現実にはしゃべらない。話者が空想している。「空想」とは「現実とはかけ離れていて、実行(存在)することができない」という意味。
・「クラムボン」や「イサド」は、宮沢賢治が自分が想像したもの。現実にいる生き物ではない。
「想像」というのは、「自分の頭の中で思ったこと・自分の考え」「そこにないものや、知らないことを心の中に思うこと」という意味。
・「五月」から「十二月」にいきなりタイムスリップをしている。現実にはどう考えても無理。非現実。
話者の頭の中ではタイムスリップも可能になる。
<B.話者が持っている・写している>
・幻灯が写っているということは、どこかにそれが写っているということ。見せるということは、話者がその幻灯を持っている。
・頭の中にあると、幻灯は見せられない。
指示 では、「今日の授業で考えたこと」をノートに書きなさい。
以上で、授業は終了するが、必要ならば授業のまとめに次のことを行う。
以下のことは、「大森修が斬るin会津」で、大森修氏と槇田健氏より教えていただいたことである。
説明 「スクリーンの位置はどこか。」をさぐるためには、押さえておかないといけないことがあります。
説明 まず、「幻灯」です。「幻灯」をそのまま「スライド」とすると「やまなし」の世界はわかりません。
発問 「幻灯」の「幻」とはどういう意味ですか。
・まぼろし
説明 そうです。まぼろしです。二枚の幻灯は、現実のものではありません。まぼろしなのです。
発問 次。4ぺ-じ3行目「小さな谷川の底を写した、二枚の青い幻灯です。」とあります。
この文の述語は「二枚の青い幻灯です。」です。では、主語は何ですか。
・ない
説明 そう、ないのです。何が「二枚の青い幻灯」なのか。先生は「私の心は」だと考えます。
・(私の心は)小さな谷川を写した、二枚の青い幻灯です。
指示 次です。最後の文に「私の幻灯」とあります。「私の幻灯」の「の」が解釈できないとできません。
「の」を広辞苑で調べなさい。
たくさん出たので、次のようにまとめた。
①所有・所属 「私の持っている幻灯」
②関係 「私に関しての幻灯」「私に関係する幻灯」
③性質 「私という性質の幻灯」
④内容 「私という幻灯」
⑤同格 「私自身である幻灯」
⑥主語を表す 「私が幻灯」
指示 このうちのどれと考えるかで、「やまなし」に対する解釈が変わってきます。
今の段階でどれだと考えますか。これだと思うものに○をつけなさい。
指示 最後です。一番最後の文に「これでおしまいであります。」とあります。「これでおしまいです。」とどうちがいますか。
・「おしまいであります。」は断定。強調している。
説明 これらのことを考えると、二枚の幻灯は賢治の心の中を表した世界、つまり心象風景だと言えます。
ですから、スクリーンの位置は話者の頭の中・心の中にあるのです。